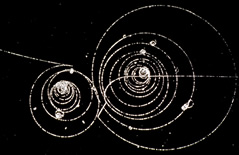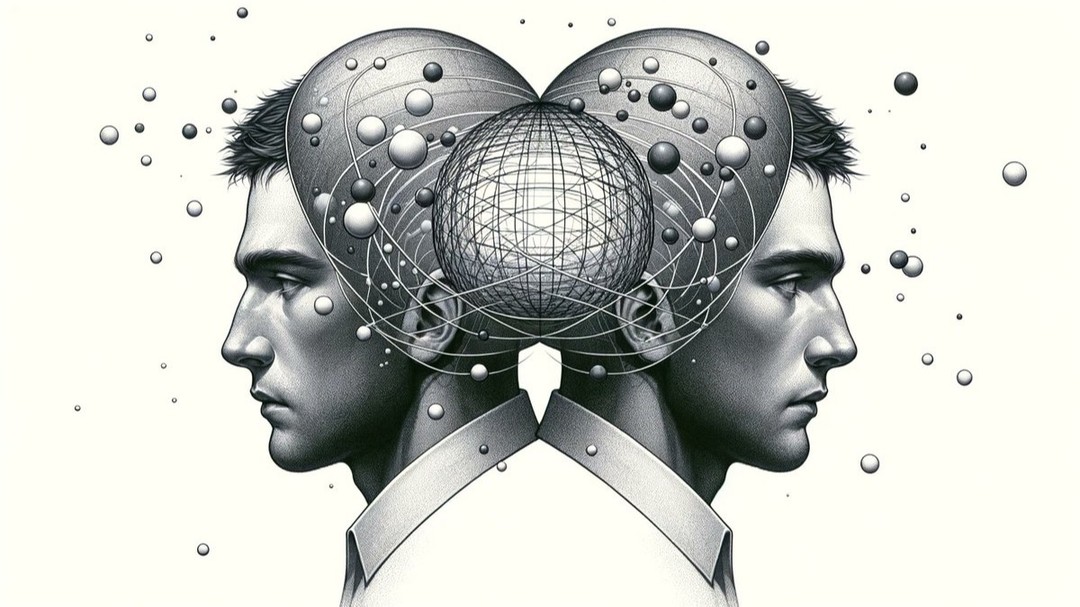1. はじめに
一時のブームは去ったものの、現在、現代思想のシーンでは新実在論と呼ばれる一連の若手思想家たちのムーブメントが脚光を浴びている。この運動の主要なメンバーは、カンタン・メイヤスー、グレアム・ハーマン、レイ・ブラシエ、イアン・ハミルトン・グラントの四人とされているが、その中でも、とりわけメイヤスーが展開する思弁的実在論(メイヤスー自身は「思弁的唯物論」と呼んでいる)は、ドゥルーズとデリダ亡き後、フランスの現代思想の潮流を受け継ぐ差異の哲学として注目を浴びており、今では現代思想の大きな潮流の一つとなりつつある。
思弁的実在論の特徴はカント以来連綿と続いてきた近現代の哲学の全面的な批判にある。メイヤスーはカントは言うに及ばず、フッサールの現象学、ハイデガーの存在論、ドゥルーズやデリダに代表されるポストモダン思想、さらにはフレーゲ、ラッセルに起源を持ちウィトゲンシュタインに始まる分析哲学の流れなども一括りにして、それらすべてが存在と思考の相関性から逃れていない「相関主義」の哲学であるとして批判する。そして、人間の思考から独立した実在について考えるために、人類が出現する以前の〈祖先以前性〉や〈原化石〉に関する議論を契機にして、人間なき世界の「実在」の在り方について思索を進めていく。ここでいうメイヤスーの実在とは、もちろん「素朴実在論」がイメージしているような物質的な存在ではない。彼が実在と呼ぶものは、たとえ人間が存在していなくても、そこに厳然と存在する何かしらの絶対的存在のことである。メイヤスーはそれを数学の思弁的な射程の中に見出し、ヒュームの因果論を根拠にしてライプニッツ由来の充足理由律を排し、カントールの超限数の概念まで持ち込んでは、世界の現出の在り方を偶然の必然性に支配された確率論的なものとして論じていく。そして、その立場を「思弁的唯物論」と呼んで極めてラディカルな議論の展開をはかるのである。
こうした思弁的な実在の方向性はポスト構造主義が打ち出した従来の存在論的差異の方向性を刷新する別種の差異の哲学と呼べるのかもしれない。しかし、そのような方向に哲学が思考を転換したとして、果たして、それがわれわれ人間にとってどのような有意味性をもたらすのかは定かではない。さらに言えば、メイヤスーはハイデガーやドゥルーズの存在論についても相関主義の中に一括りにしているが、その論拠に関しては詳しく示しておらず、この辺りについてはかなり粗雑な議論になっているように思われる。
ハイデガー哲学の基本的なコンセプトがニーチェのプラトン主義の転倒にあるのは周知の通りである。ハイデガーはプラトンのイデア論が持つ〈イデア/仮象〉という価値の優先順位を〈仮象/イデア〉へと転倒させたニーチェを高く評価するものの、それでもなお〈感性的なもの〉と〈非感性的なもの〉との優劣の関係の中に世界の成り立ちを見るニーチェを「最後の形而上学」として批判し、イデアと仮象の区別を反故にする存在の一義的な在り方を存在論的差異の哲学のもとに模索した。一方、ドゥルーズはこうしたハイデガーが立てた新しい論点を認めつつも、ハイデガーの思考性の中に見られる同一的なものへの回収を嫌い、そこに〈潜在的なものの反-現実化〉という新たな視座を導入することによって、思考する主体の同一性から逃れうる非人称の哲学の可能性を探った。つまり、両者はともにプラトン主義の転倒というテーゼを梃子にして、〈経験的なもの〉と〈超越論的なもの〉との相関的循環から逃れる、いわばその相関性の外部を存在論的差異の名の下に指向した哲学だと言えよう。彼らのこうした脱-相関的思考のベクトルを相関主義の名の下に一括りにし、カント哲学やフッサール現象学、分析哲学などの主体性の哲学と果たして同列に並べて語れるのかどうか、この部分ははなはだ疑問が残るところである。
この小論では、メイヤスーの相関主義批判の論拠のたたき台となった「祖先以前性」や「原化石」についての議論のあらましを取り上げ、ハイデガーとドゥルーズの存在論がメイヤスーのいう相関主義の範疇には決して含まれるものではなく、むしろ、メイヤスーの思考の方向性とは正反対の方向性に相関主義との切断を見ていた別の意味での思弁的実在論であるということを論じてみたい。言うなれば、相関主義から脱して実在を思考するベクトルには、ハイデガーやドゥルーズのように経験的なものと超越論的なものからなる相関の機構を反転させる方向と、メイヤスーのように、これらの相関自体を排除して、まったく別な場所に実在を措定する方向とのオルタナティブ(二者択一性)があるということである。
2. 思弁的実在論の議論のあらまし
まずは、メイヤスー自身による相関主義についての説明から始めよう。
「私たちが「相関」という語で呼ぶ観念に従えば、私たちは思考と存在の相関のみにアクセスできるのであり、一方の項のみへのアクセスはできない。したがって今後、そのように理解された相関の乗り越え不可能な性格を認めるという思考のあらゆる傾向を、相関主義と呼ぶことにしよう。そうすると、素朴実在論であることを望まないあらゆる哲学は、相関主義の一種になったと言うことができる」(1)
メイヤスーのいう相関主義とは、一言でいうなら、われわれが外的に認識している世界には常に私たちの思考がつきまとっているとする考え方のことをいう。つまり、人間の思考抜きに世界は存在しないし、また、世界なしに人間の思考も存在することはできない。そう主張する立場のことと言って差し支えない。このような立場からすれば、人間の思考は人間が存在しないところでの存在について考えることはできないことになる。しかし、そうなると、人間が存在する以前の世界について饒舌に語る科学的な言明についてはどう考えればよいのか。もし相関主義が正しいのであれば、科学的真理の探究は意味がないものになってしまう。しかし、メイヤスーはもはやそれは許されないとして、むしろ人間の思考とはいかなる関連も持たない科学的言明の事物世界を即自の世界として捉え直し、そこでの実在の在り方について思考していくべきだと言う。こうして、メイヤスーはそこに改めて「祖先以前性」と「原化石」についての問題を提起し、新しい実在を模索していくための議論の契機を作る。ここで問題とされる「祖先以前性」と「原化石」という用語のメイヤスーによる定義は以下のようなものである。
「人間という種の出現に先立つ—-また、知られうる限りの地球上のあらゆる生命の形に先立つ—-あらゆる現実について、祖先以前的[ancestral]と呼ぶことにする」(2)
「過去の生命の痕跡を示す物証、すなわち本来の意味での化石ではなく、地球上の生命に先立つ、祖先以前の出来事ないし現実を示す物証を、原化石[archifossile]、あるいは物質化石[matierefossile]と名づける。つまり、原化石とは、祖先以前の現象の測定を行う実験の物質的な支えである。例えば、放射能による崩壊速度がわかっている同位体や、星の形成時期について情報を与えてくれる光の放出などがある」(3)
そもそもメイヤスーの議論に注目が集まった理由は、こうした「祖先以前性」や「原化石」に関する問題が現代の哲学シーンにとっては、裸の王様よろしく、かなりスキャンダラスな問題であったからにほかならない。哲学者たちは科学的思考が前提としている素朴実在論的な世界を無条件で認めるわけにはいかない。メイヤスーが言うように、カント以降の哲学者たちは客観的な世界は人間の意識との相関においてそのように在るのであり、人間の意識が生まれる以前の世界の在り方については、何一つ確かなことは言えないと考えてきた。しかし、哲学は科学的世界観に内在するこのような問題に関して明らさまに批判を行うことは極力、避けてきた。メイヤスーも言うように「科学は権利上、万人が再生産できる経験に基づいているから、その意味では真であると言える」といったような曖昧な態度で対処する以外なかったのである。哲学者のこうした態度に対して、メイヤスーは「けれどもそうなると、四十五億六千五百万年前に何が起こったのか、地球の形成は起こったのか、イエスかノーか」(4)と厳しく詰め寄り、「筋の通った相関主義者ならば、科学と妥協することをやめねばならない」(5)「科学者に対して祖先以前的言明は幻想の言明であるとアプリオリに教えることができると、あえて声高に肯定しなければならない」(6)とまで言い放って、哲学者が等閑にしてきた科学的世界観についての是非を問う。確かに、このような問題は現在の哲学にとっては回答に窮する。人間の思考と存在は表裏一体で密着しているために、メイヤスーの狙い通り、この問いかけによって科学と哲学との間に隠れていた底の見えない恐ろしい深淵がパックリと口を開くのである。
では、メイヤスーはこのアポリアに対してどのような回答を用意したのか――メイヤスーはここで大きく経験科学の言説の方へと舵を切り、あっけないほどシンプルな回答を用意する。科学は祖先以前性の世界に言及することができているのであるから、数学だけが物それ自体へのアクセスを可能にしていると言うのである。そして、そのような数学が持つ力能を絶対的な実在とみなす。つまり、彼の言う思弁的実在論の「思弁」とは数学的観念が持つこのような絶対的自立性のことに他ならない。そして、「数学的観念を通してわれわれは絶対的なものを認識するという要請と新たに関係をむすばなければならない」として、数学のこの絶対的自立性を確保するためにヒュームの因果論を引き合いに出してくる。ヒュームの因果論とは一言で言うなら、「世界が現にこのようであるということは、ただ経験を通してのみ発見されるのであり、それは絶対的に必然的なものとして示されるわけではない」といったような出来事の因果関係を否定する考え方のことである。世界が現にこのような世界であることが絶対的に必然的なものでないならば、いつか、何の理由もなく偶然的に、この世界はまったく別の物理法則を持つ世界へと変化しても何の不思議もない。従って、メイヤスーが提唱する思弁的実在論の世界では「あらゆる世界は理由なく存在し、したがって、あらゆる世界は実際に理由なく他の在り方に変化することができる。それには一切理由はない」(7)ということになる。つまり、そこには、絶対的真理はいうまでもなく、法則も、理由律もすべて破棄され、それに代わってまったく理由を欠いた非理由律の世界が新しい実在として姿を表してくるのである。そして、メイヤスーは、そこから論点を一気に翻し、自然法則からもたらされる事実が安定していることの正当性を確立するために、存在=全体とは無関係な《非-全体》としての時間の固有性を主張する。そして、決して全体化することのないこの「《非-全体》を認める数学理論だけが存在論的な射程を持ち得る」(8)として、その要請をカントールの超限集合に重ね合わせ、存在の現出の形式自体を確率論的なものとして語っていくのである。結果、そこにはすべてが偶然のもとに、またその偶然が必然であるかのような必然的偶然性の支配による世界が出現する。そのような世界では、継起する瞬間瞬間がすべて偶然の連鎖なのであるから、ちょうど現代宇宙論におけるエヴァレットの並行宇宙論のような様相が展開されることになる。言ってみれば、これは究極の相対主義的世界観のようなものである。こうした突拍子もないラディカルな議論をメイヤスーは論理哲学的な手法で巧みに論証立てていくため、ついつい、その「思弁」に乗せられ、思弁的実在論が相関主義の足かせから抜け出して、即自としての外部をあたかも思考しているかのように感じさせてくるのだが、果たしてこのロシアンルーレットの化け物のような新しい実在論は哲学的に何らかの意味を持つものなのだろうか。
本稿では、このようなメイヤスーの議論に対して強い懸念を持っている。メイヤスーによる相関主義の括りがあまりに大雑把なためにはっきりしたことは言えないが、少なくとも、カント-フッサール的な超越論的主観性に依拠した相関性について言われるならばメイヤスーの指摘は至極妥当だろう。しかし、ハイデガーやドゥルーズの存在論に関して言うなら正鵠を得ているとはとても言い難い。なぜなら、存在論的差異の哲学自体が、元来、存在と思考の相関性の外部を目指した思考であり、カントの超越論哲学やフッサールの現象学とは、その射程において根底的な違いを持っているからである。しかし、メイヤスーはドゥルーズについては主観的な生の形而上学者、ハイデガーにいたっては信仰主義者として一蹴し、この両者が指し示した実在の方向性の可能性をさほど深く吟味することもなく、相関主義の中に一括りにしてしまっている。
ハイデガー=ドゥルーズの哲学とカント=フッサールの哲学の相違は、一言で言うなら存在論と認識論の違いと言い変えてもいい。その内実は一言で言うなら、存在と思考の相関性における先手後手関係を考慮に入れるか入れないかというところにある。つまり、認識論に巣食っている相関性は経験的なものが超越論的なものに従属しており、その論理の循環から逃れることができていないが、プラトン主義の転倒を念頭においたハイデガーやトゥルーズの存在論は、経験それ自体が超越論的なものへと変容する反転の位相をそのテーゼにしており、それは超越論的なものの即自的経験の思考と言っていいものである。メイヤスーは超越論的なものに実体はないとして、ただの条件として見ているが、ハイデガーやトゥルーズの存在論は超越論的なものの実体化を射程に置いた哲学である。その意味でも、相関主義との切断を果たした哲学と言っていいのではないかと思われる。
3. ハイデガーにおける〈性起〉する〈時—空〉
そもそもハイデガーが提起した存在論的差異とは何だったか。メイヤスーの実在概念との対比を明らかにするためにも、まずはその要点を紹介しておこう。近代的な思考は物を存在者として思考する。これは物を対象として捉えることを意味している。この場合、対象はまさにカント的な理性における主観の表象作用としての物であり、そこでは物は主観に従う相関物とならざるを得ない。それに対して、ハイデガーは、物はそれ自身において自立的に存在すると考える。自立的であるからには、この物は〈主観/客観〉という相関の絆からは解き放たれており、存在論的思考は物を物において独立に論じなければならない。これだけでも、ハイデガーの存在論が、カントが判断を留保した物自体としての実在の世界の奪回を念頭に置いていることが分かるだろう。
ここでハイデガーが考える物自体の世界とは、カント的に言うなら「人間の意識の成立の条件となる直観形式としての時間と空間」が生まれる以前の世界という意味であり、ハイデガーはそこに存在そのものの非隠蔽性(アレーテイア)、要は「隠れなさ」を見て取る。つまり、メイヤスーが数学的観念の絶対性を見るところにハイデガーは隠蔽されている存在の開示性を見るわけである。ハイデガーにとっては、通常の時間と空間は、存在の非隠蔽性が隠蔽されてしまったこと(存在忘却)によって存在者と同時に生じてくる従属的な二つの効果にすぎない。つまり、ここでハイデガーが問うているのは、存在者が現存在である人間の前にどのような現れの仕方をしてきたのかという、その現出の在り方である。われわれは存在の方から為される贈与を一方的に受容するのではなく、ハイデガーの言い方を借りるなら、まさに物を「それ自身のほうから現れてくるとおりに、それ自身のほうから見えるようにする」ことができなければならないのである。このような思考の境位が人間に到来することをハイデガーは〈性起(Ereignis)〉と呼んでいる。ハイデガーのこの〈性起( Ereignis)〉においては、存在者の現成は時空内部的に生起するのではなく、時間と空間の現成と同時的なものである。そして、ハイデガーは存在が持つこの現出における根源的な時間と空間の在り方を〈時—空(Zeit-Raum)〉と呼んで、感性の直観形式として与えられたカント的な時間と空間とはまったく別のものとして区別する。
「この根源的な本質における〈時—空〉は、人が通常知っている「時間」と「空間」自体のいかなるものも、まだ持っていない。しかしやはり〈時—空〉は「時間」と「空間」への展開を内に含んでおり、それも、空間と時間の数学化によってこれまで出てくることのできたものより、さらに大きな豊かさにおいて、この展開を含んでいる。どのようにして〈時-空〉から「空間と時間」へ、至るのだろうか」(9)
このように、時間と空間の現成化とその由来について問うことは、存在者と存在との関係が本来どのように組織化されているのか、まさに、その両者の存在論的差異についての思考をわれわれに促すことになる。こうした身構えを持つハイデガー哲学において「祖先以前性とは何か」と問うなら、それは「存在そのものが持った覆蔵性」以外の何ものでもないということになるだろう。事実、ハイデガーは祖先以前性を思惟以前性と称し、それを人類の思考が及ばない過去の事柄を指すものとし、「それに先んじてはそもそももうなにも思索されえないが、そこから思索の本質が始まる」(10)と論じている。そして、ここで言われる「思索の本質」こそが、カントのいう「超越論的なもの」の概念に当たるのである。カントにおいては「超越論的なもの」とは単に名ばかりのものにすぎず、実際にそれを露わにするための存在の問いが完全に断ち切られているということなのだ。だからこそ、ハイデガーは、それを経験可能なものとするために、われわれ現存在としての人間に超越論的なものを与え、条件づけしている存在そのものの内への跳躍を〈性起(Erignis)〉として呼びかけるのである。
さて、メイヤスーはハイデガーが相関主義の域を出ていない例として、この〈性起(Erignis)〉の概念を挙げ、これについても「カントから継承され、フッサールの現象学によって延長された相関性の要求に忠実なままである」(11)と書き記している。しかし、その根拠の説明になるとかなり心もとない。メイヤスーは「生起(性起)は人間と存在の本質的な結びつきであり、人間と存在は、両者の固有の存在の相互帰属によって結合している」(12)という『同一性と差異性』の中でのハイデガーの記述の一部を引用し、ここでの「相互帰属」や「結合」といった言葉尻だけをつかまえて、「ハイデガーにおいては、相関主義的ダンス・ステップが厳密に維持されている」(13)と結論するだけである。先述した通り、ハイデガーにとっての〈性起(Erignis)〉は思惟以前性の問題でもあり、それはメイヤスーが提起した「祖先以前性」の問題にも深く関わる重要な問題である。よって、当然のことながら、この〈性起(Erignis)〉なる概念は思弁的実在論が拠り所としている「祖先以前に存在したという科学的な時間性」の意味にも深く関わってこよう。にもかかわらず、メイヤスーがそのような観点を持っている気配はない。このあたりの議論の進め方を見ると、メイヤスーはハイデガーの存在論の意図を読みとれていない印象を受ける。
4. ドゥルーズの〈『襞』の存在論〉
では、一方のドゥルーズの存在論に関してはどうだろうか。先に示したようなハイデガーの存在論の内容を受けて、ドゥルーズは批判的にこの存在論の乗り越えへと向かう。ドゥルーズはベルクソンが提示した純粋持続の概念を先鋭化させ、まずはそれをハイデガーの「存在」の概念と重ね合わる。そして、ベルクソン哲学が明らかにできなかった持続の創造的運動、つまり、一元論的な持続がいかにして存在者の多様性を生み出してくるのか、その「一」から「多」へと向かう存在の機構についての考察を進めていく。ドゥルーズの思考がハイデガーのそれと大きく違うところは、差異化を通じて生まれてくるこのような世界の有り様が、そのまま人間の自我の自己同一性の解体へとつながり、旧来の主体を異他化させていくところにある。ハイデガーの場合は、差異化によって遂行される取り集め(Versammlung)の構想にこだわりを持ち過ぎたためか、それは「民族」や「大地」といったノスタルジックなイメージへと回収され、そこに存在の本来的なものの姿を見ようとして、ある意味での後退化を起こす。つまり、ハイデガー自身がニーチェを批判したのと同じ問題—————本来的なものと非本来的なものとのあいだの優劣の線引きが起こるのである。このようなハイデガーの思考はドゥルーズにしてみれば、表象=再現前化がもたらす同一性に対する従属を免れておらず、差異の思考としては徹底さに欠けることになる。
ドゥルーズは自らの存在論的差異の思考を徹底化するために、ハイデガーの〈性起〉の概念を〈出来事〉という概念へと置き換え(元来、〈性起〉自体に「出来事」という意味がある)、ストア派の哲学や構造主義、さらにはラカンの精神分析の考え方などを取り入れ、より現代的なものへと練り直していく。ドゥルーズはこうした脱-表象化された意識の経験によって生まれてくる新しい思考の現実を反転した現実という意味で〈反-現実〉と呼び、脱-主体化した非人称の主体による超越論的なものの経験を可能にする経験論、すなわち、超越論的経験論を打ち立てるのである。さらに、後期のドゥルーズに至っては、この新しい主体によって開かれてくる超越論的なものの世界をライプニッツ哲学と接続させ、モナドの絶対的内部性として活動するこの高次の経験論を〈「襞」の存在論〉として展開させていく。
「一つの襞が生命体を貫通するのだが、それは生の形而上学的原理としてのモナドの絶対的内部性と、現象の物理学的法則としての、物質の無限な外部性を分配するためである。二つの無限の集合があり、一方は他方と交わるところがない。〈外部性の無限の分割は、絶えず延長され、開かれたままである。だから、外部を脱して、内部の点的な統一性を確立しなければならない・・・物理的、自然的、現象的、偶然的領域は、全部が、開かれた連鎖の無限の繰り返しの中にひたっている、この点でそれらは非形而上学的である。形而上学的領域は彼方にあり、反復を斥ける・・・モナドは、無限に分割する事によって決して到達する事の出来ない、あの定点であり、無限に分割される空間を閉じるのである〉」(14)(〈 〉内はドゥルーズによるミッシェル・セールからの引用)
ここでドゥルーズがミッシェル・セールを引用して言う「開かれた連鎖の無限の繰り返し」というのが、相関主義が孕む相関的循環のことだと考えるといいだろう。そこで無限の繰り返しを行なわせているものは絶対的内部性として活動する超越論的原理の方なのだが、外部性を活動拠点とする経験的意識にとっては、超越論的なものを潜在的なものとしてしか把握することができない(存在忘却している)ため、相関的循環を余儀なくさせられることになる。しかし、超越論的経験においては、その反復を斥けるもの、つまり、モナドの「内部の点的な統一性を確立するもの」が登場してくる。これがドゥルーズのいうところの「永遠回帰」である。永遠回帰は「同一的なものとは反対に、すべての先行的な同一性が廃止され解消されるような世界」(15)を前提にしている。このドゥルーズ的な永遠回帰において非人称的なものへと変身した主体は、生の形而上学的原理としてのモナドの絶対的内部性たる超越論的なものそれ自体の経験を可能にしていくことになる。そして、この絶対的内部性は〈巻き込み(implication)〉と〈繰り広げ(explication)〉という襞化の運動によって、内部=存在の覆蔵性と外部=存在の非-覆蔵性との間に新たなる交通空間を開通させ、新しい創造の名のもとに、あたかもパイ生地を練るようにして物質を〈時-空〉の開花運動と共に生成させていくのである。こうしたドゥルーズの〈「襞」の存在論〉には、ハイデガーが二重襞として表現したあの〈時—空〉の概念がスピノザの能産的自然の哲学と共に手を取り合いながら、存在者の現出のビジョンとして関わっている。そして、この流動的な存在論のイメージはドゥルーズ=ガタリの『千のプラトー』においては、より壮大に存在論的地層の考古学的一大アレンジメントとして表現されていく。精神と物質をめぐるこのようなダイナミックな自然学は、カント哲学やフッサール現象学のような超越論的主観性に固執した哲学には見られないものであり、メイヤスーが言うような主観主義的形而上学の枠に決して収まり切れるものではない。
現出する自然をこのような視力で貫くドゥルーズからすれば、メイヤスーに対する批判は容易いだろう。たとえば、メイヤスーが語る「祖先以前性」に言う「以前」とは一体どのような”時間軸”において言われる「以前」なのだろうか。メイヤスーは45億年前に地球が生まれたとか、135億年前に宇宙が誕生したなどといった科学的な言説を無骨に議論のテーブルの上に乗せてくるが、こうした祖先以前性の規定がドゥルーズのいう同一性の思考の枠を逃れていないことはすぐに分かる。ドゥルーズによれば、同一性の思考には「概念に対する同一性」「諸述語に関する対立」「判断に関する類比」「知覚に関する類似」という四つの足枷が常にはめられている。例えば、「祖先-以前」には「祖先-以後」が対立し、それらは当然のことながら延長的時間という概念の同一性に依拠している。また、以前か、以後か、という判断が類比によるものであることは言うまでもない。われわれが科学法則から意味が汲み取れるのも、こうした同一性の思考の裏付けがあるからに他ならない。メイヤスーは、存在論の思考がこのような同一性の外部の思考について言われるものであることをきちんと押さえた上でドゥルーズを相関主義者として見なしているのだろうか。科学が祖先以前性の世界について物理法則を通してどのように記述しようとも、それが通常の時間と空間の概念に支えられた「物質の無限な外部性」についての物理法則である限り、ドゥルーズが語るような存在論的差異として活動する〈反-現実〉に触れることは全く持って不可能であると言えるだろう。
5. 相関の外部が持つ二つの思考のベクトル
さて、メイヤスーの祖先以前性や原化石に関する議論が孕む問題点をハイデガーとドゥルーズの哲学が擁する〈時-空〉概念から簡単に述べてきたわけだが、これらの批判もメイヤスーから見れば相関主義の枠内のものとして片付けられてしまう可能性も否定できない。実際、メイヤスーはこの〈時-空〉が持つ時間性の概念を「ひっくり返された時間のでっち上げ」(16)として揶揄し、そして、「この奇妙な知恵によって科学の時間性では把握可能だった祖先以前性(実在)の様態を把握することができなくなったのだ」と言っている。そして、「わたしたちより前に到来するものは私たちより前に到来する」(17)と断言して、超越論的なものへの遡行ではなく、純粋な順序としての科学の時間性の正当性の復活を訴え、哲学においてのその奪回こそが、実は存在の時間性に対する「恐るべき現出のパラドックス」になっているのだと切り返す。つまり、メイヤスーはハイデガーやドゥルーズの存在論の時間を承知の上で、それでもなおかつ科学的時間の順序性を擁護し、所与それ自体が非存在から存在へと移行する時間を、科学的時間の中でどのように考えるべきか、その思考を要請しているのである。
「もし、何らかの意識が地球上の生命の出現を観察したならば、所与の出現の時間は、所与のなかの出現の時間となっていただろう。ところで、ここで考えられている時間とは、まさしくそこにおいて時間意識としての意識それ自体が出現した時間である。というのも、原化石の問題とは、生命を持った有機体の誕生についての経験的な問題ではなく、贈与の到来に関する存在論的な問題だからである。そして、より先鋭化するならば、問題は意識に先立って存在すると考えられる時空間のなかで、科学が特別な困難なしに、意識の到来とその贈与の時空間的な形式の到来をどのように考えることができるのか、ということを理解することである。とりわけ、それによって、科学は、贈与なき状態から、贈与がある状態への移行が実際にそこで起こった時間を思考しているのだと理解されるのである」(18)
ここで示されているように、メイヤスーにとっての「意識に先立って存在すると考えられる時空間」とは、科学が扱う数学によってのみ記述可能となるような世界のことである。確かに、この相関的な外部に存在する生成の時間についての是非が問題とされなくてはいけないのだが、そこにおいて科学が扱う数学を思弁的実在と考えることは良しとしても、メイヤスーがその時間を贈与された時空間的な形式の中に回収させて考えていることは否定できない。なぜならば、メイヤスーが例として挙げている放射性元素の崩壊速度や熱ルミネセンスの諸法則などの物理法則を成り立たせている数式は、あくまでも順序立てられた時間を前提にして導出された数式であり、これはさきほどのドゥルーズの言い方を借りるなら「物質の無限な外部性を分配」するための数学が導き出した数式にすぎないからである。数学の絶対性を訴えるのであれば、むしろ、ドゥルーズが超越論的領野として指し示した「モナドの絶対的内部性」を表現する数学の力能についての思弁の方が遥かに重要ではないかと思われる。ドゥルーズはそのことに十分に気づいており、だからこそ自らの存在論を高次元の連続的多様体の理論として論じ、「哲学とは多様体の理論である」とまで言い切り、哲学と自然科学との接合を企図していたのである。この点から考えれば、祖先以前性を数学的な思弁として思考する射程においても、メイヤスーよりドゥルーズの方がはるかに奥深い思弁的実在に触れていると言ってよい。
周知の通り、現代の量子論おいては、もはや時間を古典的な順序立てられた時間として思考することはできない。群論的構造をその基盤に持つ現代の量子論の状況は、祖先以前性という従来の時間軸に囚われた方向に実在を探すメイヤスーの存在論よりも、モナドの内部性における差異の系列に注目したドゥルーズの存在論の方にはるかに適合しているように見える。メイヤスーが群論や位相幾何学、微分幾何学等、現代の数学的な体系全体を含めた上で数学の絶対性を主張するのであれば、メイヤスーの思弁的実在論の主張は極めて面白いものになり得ると思えるが、彼のいう数学の絶対性はカントールの超限集合論をベースにした確率論的思考のみに偏向、収斂しており、あくまでも時空間の先行を条件とする「物質の無限な外部性」における同一性の数学のようにしか見えない。それは、メイヤスーによる祖先以前性の時間的位置づけが「第一世界が物質世界、第二世界が生命世界、第三世界が思考世界」といったように、科学的な進化観に準じた直線的時間を前提にして現象界の進展を並べていることからも容易に窺えよう。
ハイデガー=ドゥルーズの思考からすれば、科学の時間性が持つこのような後方投射は祖先以前性の時間の在り方を大きく歪曲させているように見えるはずである。こうした思考は純粋に、史学的ないし、先史学的な方法が支配する歴史的思考に準ずるものであり、ハイデガーに言わせるなら、これは「全面的に因果性において思惟しており、生や体験可能なものを因果的な検算にとって通路づけられるようにし、ただその中にのみ歴史的な知を見る」(19)方法にすぎない。メイヤスーが数学的なものを絶対とすることにはそれほどの異論はないが、彼の議論がそれなりの一貫性を持つためには、科学的時空間の先行性自体を数学自身が数学的に証明しなければならなくなるだろう。しかし、おそらく、それは難しい。それこそ集合論的に考えたとしても、物理的時空を記述する実数世界はモナドの内部性たる〈時-空〉を記述する複素数の世界の一部分にすぎないことを当の数学自体が示しているからである。
ドゥルーズの立場からも同じことが言える。ドゥルーズにとっての科学的時間は『差異と反復』において語られたように、「空虚な時間の形式」「発狂した時間」「蝶番が外れた時間」にすぎない。それは単なる物差しと化してしまった時間でしかなく、そのような時間の形式で祖先以前性や原化石の存在を記述する物理法則は単なる結果の産物でしかない。つまり、メイヤスーの問題提起の前提となっている時間性には、存在の思考に不可欠な根源的時間=即自的過去がまったく考慮されておらず、そのような〈根源〉を欠いた時間はすべてクロノロジックな時間概念でしかないということなのだ。少なくとも『有限性の後に』で主張されている内容を見るかぎり、メイヤスーは根源的時間=即自的過去が祖先以前性や原化石の問題にどのように関係してくるのかについては何も吟味していないし、また、その必要性も感じていないかのようである。重要なことは、科学の時間性へと時間の順序を戻すことではなく、量子論など科学が発見しつつある新しい時間性を、根源的時間が活動する超越論的領野の方へとアジャストさせることができるような存在の思考線を哲学が見出すことなのである。
まとめておこう。ハイデガー、ドゥルーズがイデアと仮象の関係を問題にするという意味において、相関主義者の枠内に括り得るとしても、そこにプラトン主義の転倒というフィルターをかけ、さらには、相関性そのものを経験的なものの位置からではなく、存在の開示や超越論的経験論という形で高次の経験の可能性の上に置くならば、メイヤスーが言うように「主体は、世界のなかに位置付けられることでのみ、超越論的になる」ことはない。逆に、超越論的なものの経験そのものが主体を世界のなかに位置づけるようになるのである。まさに、そうした経験的なものと超越論的なものの相関関係が反転した世界の到来を予言したのがハイデガー=ドゥルーズであった。哲学が脱-人間化を目指す限り、このような思考のベクトルを失うことは哲学自体の死に繋がると言っても過言ではないだろう。メイヤスーが思弁的実在論に見る実在の方向性と、ハイデガーやドゥルーズが存在論的差異の中に見る実在の方向性とは、相関主義の外部における真反対の方向にあるベクトルであることを哲学は知らねばならない。
ニーチェは「来るべき二百年はニヒリズムの時代になるだろう」と予言して、この世を後にしたが、彼が一つの中継点となって登場してきたハイデガー、ドゥルーズに代表される反転の存在論も、この寄る辺なき偶然性に満たされた21世紀のニヒリスティックな思想潮流の中に泡沫のように姿を消していく運命にあるのだろうか。ドゥルーズはいみじくも分析哲学のことを哲学の暗殺者と呼んでいた。メイヤスーらに代表される科学主義や論理主義に強く影響を受けた新実在論の思想的潮流が哲学的精神の刺客とならないことを心から祈りたい。
〈参考文献〉
- (1) カンタン・メイヤスー(2016)『有限性の後で』人文書院,16
- (2) カンタン・メイヤスー(2016)『有限性の後で』人文書院,24
- (3) カンタン・メイヤスー(2016)『有限性の後で』人文書院,24-25
- (4) カンタン・メイヤスー(2016)『有限性の後で』人文書院,34
- (5) カンタン・メイヤスー(2016)『有限性の後で』人文書院,35
- (6) カンタン・メイヤスー(2016)『有限性の後で』人文書院,36
- (7) カンタン・メイヤスー(2016)『有限性の後で』人文書院,24
- (8) カンタン・メイヤスー(2016)『有限性の後で』人文書院,213
- (9) マルティン・ハイデガー(2011)ハイデガー全集第65巻『哲学への寄与論考』創文社,418
- (10) マルティン・ハイデガー(2011)ハイデガー全集第65巻『哲学への寄与論考』創文社,16
- (11) カンタン・メイヤスー(2016)『有限性の後で』人文書院,19
- (12) カンタン・メイヤスー(2016)『有限性の後で』人文書院,20-21
- (13) カンタン・メイヤスー(2016)『有限性の後で』人文書院,21
- (14) ジル・ドゥルーズ(1998)『 襞──ライプニッツとバロック』河出書房新社,51
- (15) ジル・ドゥルーズ(2016)『差異と反復・上』河出文庫,122
- (16) カンタン・メイヤスー(2016)『有限性の後で』人文書院,205
- (17) カンタン・メイヤスー(2016)『有限性の後で』人文書院,205
- (18) カンタン・メイヤスー(2016)『有限性の後で』人文書院,41
- (19) マルティン・ハイデガー(2011)ハイデガー全集第65巻『哲学への寄与論考』創文社,158