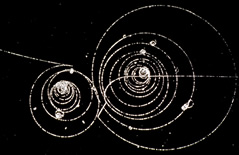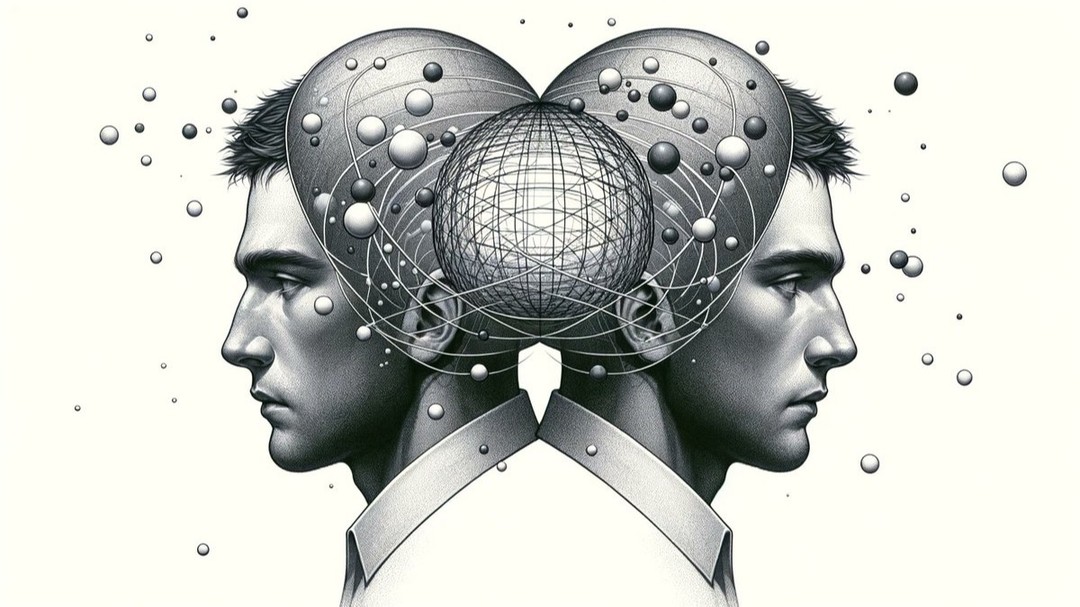1. はじめに
『差異と反復』で論じられた〈差異化=微分化〉の概念が、襞の物質論を展開するドゥルーズ哲学において最も重要な鍵概念となっていることを否定する者はおそらく誰もいないだろう。しかしながら、この微分概念の使用法が物理学者アラン・ソーカルらによって手厳しい批判を受けたのも周知の通りである。あれからすでに20年近い歳月が経過した今もなお、ソーカルらの批判に対する反論がドゥルーズの研究者たちから折に触れてなされてはいるものの、未だその批判の乗り越えに成功しているとは言いがたい。というのも、それらの反論のほとんどが哲学的原理にもとづいた物理学批判に終始している感があり、物理学の内実に根付いたところでの生産的な議論の進展には至ってはいないからである。
ドゥルーズ哲学が自然科学の哲学へと拡張の可能性を開いていくためにも、わたしたちは哲学的原理に固執する議論に止まるのではなく、成功を収めた物理学理論を包含するような哲学的理路をドゥルーズの諸概念の中に見出していく必要があるのではないだろうか。また、その作業においてのみ、ソーカルらの批判に対する乗り越えが可能になるようにも思える。この小文では、こうした問題意識を持ちつつ、ドゥルーズが『差異と反復』で展開した〈差異化=微分化〉のイデア論を自然科学の文脈でより実り多い議論としていくための基本となるアイデアを提出してみたい。
2. ドゥルーズにおける差異と微分
ドゥルーズにとって差異とは「所与がそれによって与えられる当のもの」(※1)のことである。これは、わたしたちが普段経験しているような二つの事物間にある差異を指すのでなく、事物それ自体における本性上の差異のことを意味している。本性上の差異とは「自己に対して差異を生ずるもの」(※2)のことであり、周知の通り、これはベルクソン哲学における持続概念のことを指している。ベルクソン=ドゥルーズにとって、持続は「われわれを一気に精神のなかに置く記憶の方向」(※3)へと運ぶものであり、この持続が息づく場所は「われわれを一気に物質の中に置く知覚の方向」(※4)である延長世界とは明確に区別されるべきものであった。では、思考はいかにして同一性の場としての時-空間的連関からこの差異=持続が息づく場所へと赴くことができるのか。ただ「直観において思考する」としか言い表せなかったベルクソンに対して、ドゥルーズはこの持続概念を空間と結びつけるために『差異と反復』において独自の微分論を持ち出してくる。
ドゥルーズにとって、微分はもはや無限小への漸近を意味するものではない。ドゥルーズは、ニュートンはもちろんのことライプニッツの微分概念をも退け、ボルダス=ドゥムーランの解釈を足がかりにして、微分を「善悪の彼岸にある唯一の計算法」(※5)とまで言い切り、《理念》を露にするための「切断」の作用と見なす。これはドゥルーズが微分を科学的な準拠平面ではなく、強度的=内包的な哲学的な内在平面において思考していたことを意味するのだが、肝心のその根拠についての説明はかなり難解であり、その理路が哲学的に判明なものになっているとは言い難い。さらに言えば、ドゥルーズは、ものの立ち現れの次元が存在の諸領域によってそれぞれ異なっていると考え、そこに関わる理念もそれぞれ固有の微分法を持っているとし、物理学的《理念》から、生物学的《理念》や社会的諸《理念》へと何の具体的説明もなしに、この独自の微分概念を適用させていく。この流れだけを見れば、確かにドゥルーズの語る微分は数学用語の無闇な濫用と見られても致し方ない部分もある。
しかし、ドゥルーズの〈差異化=微分化〉論の中核になっている「内包量が外延量を生み出す」という〈差異化=微分化〉から〈異化=分化〉への産出原理については、現代物理学の観点から見ても決して無意味なものとして退けられるものではない。関連すると思われる事項を幾つか挙げてみよう。
3. 差異としての虚数単位「 $i$ 」
リーマンが『幾何学の基礎をなす仮説について』において予見していたように、現代物理学が実在と見なしている時-空間的連関はもはや「無限小部分における空間の量的関係が幾何学の仮定に従わない」(※6)ものとなっている。というのも、実数直線に対応させられた延長的空間や直線的時間の微分化には強固なカベが存在しており、そこではもはや無限小という極限を取ることは許されなくなっているからである。この禁止を強いるものが、ハイゼンベルグの不確定性原理から要請される不確定性領域というものであり、これが同時に素粒子を構成する場の領域にもなっている。
この領域の最も単純なものは幾何学的には波動関数の母胎となっているオイラーの公式 $e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$ が描く円環によって規定されているのだが、オイラーの公式自体は複素関数であって、ドゥルーズが言う $\frac{dy}{dx}$ のような差異的=微分的な関係比によって規定することができない代物である。と言って、微視的な領域に差異が存在しないと言えば全くの嘘になる。むしろ、こうした複素数の場で構成される素粒子の存在によって微視的領域においては差異がより明白なものとなっていると言った方がよい。しかし、繰り返しになるが、そこに見られる差異とは実関数の微分化によって露わになるものというよりは、むしろ、端的に実数空間と複素空間の間における差異なのである。より正確を期せば、実数 $x$ と複素数 $x+yi$ の差異としての虚数単位「 $i$ 」それ自身で形式化される虚的空間のことと言っても差し支えないだろう。
自然界における極小領域が虚数= $i$ を含み持つ複素関数でしか記述することができないというこの物理学的現実は、ドゥルーズの差異化=微分化の概念を物質と接続していくに当たって極めて重要な概念となっているのではないだろうか。おそらく、晩年のドゥルーズもそのことには十分気づいていたのではないかと思われる。ドゥルーズは『哲学とは何か』で、外延量が示される形式を横座標(アプシス)(※7)と呼び、同じく強度=内包量のそれを縦座標(オルドネ)(※8)と呼んでおり、この横と縦の両座標の関係にドゥルーズが実数軸と虚数軸からなる複素平面のイメージを重ね合わせていたことは想像に難くない。
実際、量子力学では外延量としての位置は波動関数に $x$ を直接、掛け合わせることで求めることができるが、内包量としての運動量の方は波動関数を位置で[微分]しなければ導出することはできない。そして、この微分化の操作自体が $\hat{p}→-i\hbar\times\frac{\delta}{\delta x}$ という形でそのまま運動量 $p$ の量子化を指している。位置 $x$ は実軸=横座標で規定されるので、波動関数 $\psi(x)$ の位置 $x$ での微分の幾何学的イメージは横座標=実軸を縦座標=虚軸へと90度回転させるイメージになるのだが、このイメージ自体が外延量としての位置を内包量としての運動量へと変換する意味を持っている。ドゥルーズにとって外延が同一性の領域であり、内包が差異化の領域であったことは言うまでもない。ここに、位置 $x$ での微分化がドゥルーズのいう差異化と全く同じ意味を持って、文字通り〈差異化=微分化〉として、外延量を内包量へと反転させる操作となっている物理学的な事実をわたしたちは決して見逃すべきではない。
さらに付け加えるならば、量子力学において、この位置と運動量は交換関係において文字通り[差異]を持っている。交換関係とは量子力学の基本原理の一つであり、これは位置と運動量や時間とエネルギーといった正準双対な物理量の演算子において、それらを相互に入れ換えた積同士の差を示すものである。位置と運動量の場合ならば、それは $\langle\hat{x},\hat{p}\rangle=\hat{x}\hat{p}-\hat{p}\hat{x}=i\hbar$ ( $i$ は虚数単位、 $\hbar$ はディラック定数)として表され、交換子積は非可換となり $i\hbar$ という差異を持つ。
ここで位置演算子を外延的なものへの変換、運動量演算子を内包的なものへの変換とそれぞれ解釈すれば、この差異は外延的な力が優位となった場と内包的な力が優位となった場との間の差異を表現しているものとも考えることができる。これはドゥルーズの言い方を借りるならば、《理念》(構造-出来事-意味=方向)と表象=再現前化とのあいだにある差異(※9)そのものの物理学的表現と見なすこともできるのではないだろうか。もしそうだとすれば、ここにおいても虚数単位「 $i$ 」が差異化の本質として絶対的な役割を担っているということになる。
4. 早すぎたドゥルーズ
もう少し例を挙げておこう。複素関数としての波動関数 $\psi$ が $\psi^*\psi=|\psi|^2$ というかたちで粒子の存在確率として解釈されていることはよく知られている事実だが、実際、量子力学においては粒子の位置の情報は粒子の状態を表す波動関数 $\psi$ のこの円環的=内包的な形式の中に[巻き込まれて]存在させられており、運動量 $p$ やエネルギー $E$ といった粒子の物理量は波動関数 $\psi$ を位置 $x$ や時間 $t$ で[微分]することによって、逆に[繰り広げ]られたものとして導出されてくる。
つまり、素粒子空間それ自体をドゥルーズのいう潜在的多様体と見なせば、潜在的なものの側から差異化=微分化して、いかに異化=分化が生起してくるのかというドゥルーズが論じた「差異の差異化」のプロセスが量子力学では極めて直裁的に表現されているわけである。さらに言うならば、場の量子論で用いられるディラック方程式は $SU(2) \times SU(2)$ (複素2次元ユニタリー群同士の直積)という群の構造を背景に持っており、この構造性の中には2成分スピノルのテンソル積からローレンツ変換を通して時間と空間の延長性がもたらされてくる仕組みが内在させられている。また、R・ペンローズのスピンネットワーク理論でもスピノルが構成する内包性から時空の延長性が規定されるという構造性が明らかにされており、現在では、このスピンネットワーク理論のアイデアはループ量子重力理論の中にも取り込まれ、量子論と相対論の統一には欠かせない考え方となっている。こうした最先端の物理理論から見るなら、時-空間的連関の場としての外延性はすでに内包性に組み込まれて存在しているものと考えても何ら差し支えはなく、もはや、現代物理学も時空という同一性の世界を世界の根拠としてはいないとも言える。
こうした現代物理学の現況をドゥルーズ風に論じるなら、存在世界の中にあって素粒子は一つの〈解〉であると同時に、それ固有の〈解〉の解決可能性を規定する〈問題〉の場をも同時に表現しているという言い方もできるのではないだろうか。もし、ドゥルーズの〈差異化=微分化〉の概念の説明に不備があるとするなら、それはソーカルが指摘するような数学や物理学的知識の濫用というよりも、ドゥルーズの思考に物理学の表現形式がまだ追いついていなかっただけのことであり、『差異と反復』で示されたドゥルーズの微分に対する直観は現行の物理学的現実に即したものであるようにも見て取れる。要は、ドゥルーズは早すぎたのである。
以上、紙面の許す限りにおいて、思いつくままドゥルーズの〈差異化=微分化〉と現代物理学との初歩的関連について書き記してみた。もちろん、ここで行なったささやかなる示唆は、哲学的思考の内容を規定するに当たって実証科学を頼っており、「哲学的思考の無条件性」からは逸脱するものである。しかし、ドゥルーズが言うように、世界がもし〈巻き込み〉と〈繰り広げ〉という差異化の絶え間ない反復によって襞化されているのであれば、同一性として繰り広げられた世界の構造性に立脚して、差異化の論理立てを行なうのもまた正当な思考のプロセスと言ってよいのではないだろうか。別の言い方をすれば、ドゥルーズが『差異と反復』で示したように、物理学が扱うような〈空虚な時間の形式〉が出現してきてこそ永遠は回帰の道を作り出すことができるのであり、〈繰り広げ〉という〈異化=分化〉の世界から、いかにして〈差異化=微分化〉への〈巻き込み〉が行なわれていくのかというその理路が、哲学よりもむしろ現代物理学が提示し始めている諸理論を通して明らかになってくるということもあり得ないことではない。
その意味で言えば、現働的世界において実質的無限小ともいうべきプランクスケールの世界で虚数「 $i$ 」を含みもって活動している素粒子構造としての複素多様体は、ドゥルーズがいうところの「問い=イデア」であり、それらが実数化させられて出現している自然界のすべては「解」であるという言い方も可能だろう。そして、もしそうならば、わたしたちは、延長世界に対して差異化させられた持続がどのような形で素粒子へと接続しているのかを明らかにすることによって、ミクロ世界から順に自然界を「問い」へと変換していく作業へと赴かなくてはならない。その作業によって世界が「問い」の構造を露わなものにさせ始めたとき、わたしたちはドゥルーズが垣間見ていたあの内在平面への侵入を果たしている自分自身を知ることになるのである。
〈参考文献〉
- (1) ジル・ドゥルーズ(2007)『差異と反復・下』河出文庫,156
- (2) ジル・ドゥルーズ(2000)『差異について』青土社,40
- (3) ジル・ドゥルーズ(1989)『ベルクソンの哲学』法政大学出版局,18
- (4) ジル・ドゥルーズ(1989)『ベルクソンの哲学』法政大学出版局,18
- (5) ジル・ドゥルーズ(2007)『差異と反復・下』河出文庫,45
- (6) ベルンハルト・リーマン(2013)『幾何学の基礎をなす仮説について』ちくま学芸文庫,34
- (7) ジル・ドゥルーズ/フェリックス・ガタリ(1997)『哲学とは何か』河出書房新社,172
- (8) ジル・ドゥルーズ/フェリックス・ガタリ(1997)『哲学とは何か』河出書房新社,172
- (9) ジル・ドゥルーズ(2007)『差異と反復・下』河出文庫,69