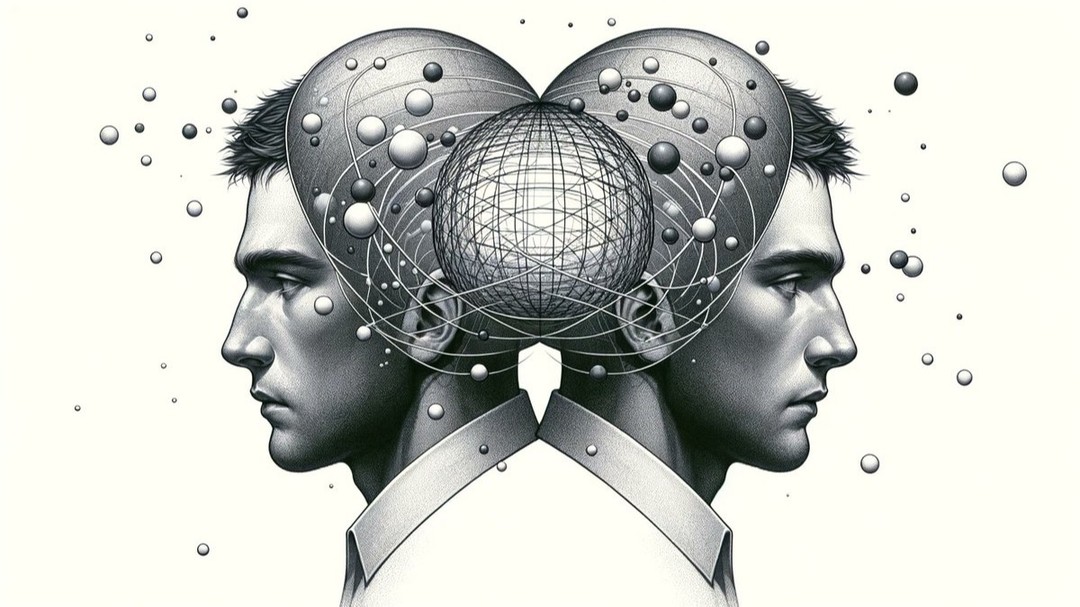アルケー、十字架、イエス・キリスト
ルシファーとしての光は左右方向に横切る光。それは秒速30万Kmとしての光。
ルシフェルとしての光は奥行き方向に存在する光。それもまた秒速30万Kmとしての光。
これら二つの光の違いとは一体何か――。
奥行き、つまり身体にとっての「前」という方向性は左-右でも上-下でもない何か特別な方向性です。僕らの見るという行為はこの「前」という方向性においてしか成立することはありません。現象とは私たちの身体の「前」で光として開示している何ものかです。ハイデガーという哲学者は『存在と時間』という著書の中で、「現象」を「自らをそれ自身に則して示すもの」として規定し、存在を現象の最中(さなか)にもたらすことを現象学の根本課題と見なしていました。存在は、あらゆるものが現出してくるその根拠として先行的に了解されているという意味では、最も自明であり、文字通り現象の名にふさわしいものですが、「わたし」という自我が出来上がったのちに認識される世界においては、現象は姿を隠し、それは匿名的に機能し隠蔽されてしまいます。時空という名において捉えられる「前」と、時空が意識に上がる以前にある「前」とは、その意味で全く違うものとして考える必要があるわけです。
奥行き方向に左-右方向と同じ「幅」という概念を与えることによって、そこに距離を持たせることは、現象の意味そのものを見えなくさせてしまいます。現象とはフッサールも見抜いていたように、いかなる臆見(ドクサ)をも与えられる以前の裸形の「前」のことであり、この純粋知覚とも呼べる現象は視野空間上でペタンと二次元の面に潰され、薄い皮膜(アンフラマンス)のようなものとして存在させられています。前回、私たちにとって奥行き方向とは時空の方向でもあり、そこには空間的距離とともに時間の経過も含まれていると言いました。とすれば、奥行き方向が一点で同一視されているというこの知覚的現実は、そこにすべての時間的経過をも内包している、ということになります。「わたし」がこの世に生を受けたのがたとえ50年前だとしても、この純粋知覚の中に含まれている奥行きという空間の深みの中には137億年という宇宙開闢以来の時間の流れが一緒に畳み込まれているということなのです。つまり、奥行き方向に存在する光においては、「今、ここ」と宇宙の始源の場所とは同じものとして考える必要があるわけです。僕がいつも「始源(アルケー)」と呼んでいるのはこの薄い皮膜、存在の皮膚とも呼べる「光」のことを言います。
アルケー=光。この覚知に至ることがヌーソロジーでいう「人間の外面の位置の顕在化」です。今まで人間の意識の営みの中で隠蔽されていたほんとうの主体が姿を現すのです。この奥行きにおいての無限小の厚みの中に、今という永遠が存在している。そして、そこが「わたし」という存在の根元的なプラットフォームになっている。現存在としての人間が生きる場所にはこのような永遠が常にセットになって張りついています。これをクリスチャンならば「我、神とともにここに居ます」と表現することでしょう。エマニュエルの神のことです。哲学者であれば「不動の大地」と呼ぶことも可能でしょう。こうした思考のもとにおいてのみ、何故に相対論において光速度が絶対的な役割を果たしているのかが分かってきます。物理学者たちがその解釈を放棄している4次元不変距離(ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 – c^2dt^2 ds^2 = 0)の本質的な意味が見えてくるわけです。
目の前で無限小の厚みにまで潰された時空。これが現象の基底としての光の正体であり、その光が持つ速度のもとでは時計の針は止まり、空間は無限小の長さにまでに縮まり、そこに4元ベクトル=ゼロの世界が出現してきます。これが光のスピンの本性です(正確にはħ/ディラック定数)。つまり、何が言いたいのかというと、一点同一視された奥行き方向としてのこの4次元こそが、アインシュタインが言うところの「無限大の速度としての役割を演じている光」そのものの意味だということです。そして、時空に対してこの永遠が直立した場所こそが時間の流れ自体を感じ取っているほんとうの主体の位置にほかなりません。要は、ほんとうの主体とは見ているものでも、見られているものでもなく、見ることそのものの中に含まれる、言わば逆光の光だということなのです。このことに人間の意識が気づいたとき、すべての人間は創造を開始する者、つまり、アルケーとしてのイエス・キリストへと変身することが可能になります。
コ : 見ること自体が「真の主体」なのではないですか?
オ : はいそうです。有機体(カタチのない精神)が最初のカタチを持ったということです。
このとき、永遠の相のもとに顕在化してくる非物体的形相。これがOCOTが「カタチ」と呼ぶ、形本来の形のことです。このことは、幾何学とは本来、永遠という場所性の中においてしか意味を持ち得ないということを物語っています。冷静に考えてみればすぐにわかります。人間の認識が時空の中でカタチを構成するのは原理的に不可能です。たとえば、僕らが地球と月を結ぶ38万kmの長さの線分をイメージするとしたらどうでしょう。たとえその線分を光速度で追いかけたとしても、時空の中では1.3秒ほどの時間かかってしまうことになります。しかし、実際の意識を確かめてみれば分かる通り、地球と月を結ぶ線分を想像するのに時間は一切必要としません。カタチとはその大きさがどのようなものであれ、一瞬で即時に把握されている何物かです。また、一瞬で把握されなければカタチという概念自体が意味を持たないものになってしまうことでしょう。正4面体を構成する4つの頂点を認識するとき、それぞれの点の把握にタイムラグがあれば、僕らは正四面体というカタチについて何も言えなくなってしまいます。ほんとうの主体とは永遠性のことであり、この無時間の主体の位置の連携によって初めて幾何学というものが構成されてくるのです。
オ : 人間の意識はカタチを見る方向に入っています。わたしたちのいうカタチとは見られるものではなく、見ているもののことなのです。
目の前に表れた視野空間上にx軸とy軸で刻まれた不可視の十字架をそっと置くこと。そして、そこで磔刑に処されている光の身体の意味について考えること。さらに言うならば、そこに垂直にイメージ化されている3次元目のz軸方向の意図について深く思考すること。このz軸方向としての幅と同一化してしまった空間的奥行きとは、イエスの脇腹に刺されたロンギヌス(カシウスの方がいいかも)の槍のことであり、人間の意識をシリウスに接続させることを妨げている深淵のことなのです。この深淵の支配者が時間であり、人間という次元の本性です。――つづく