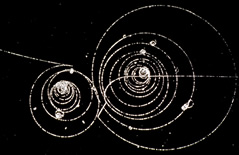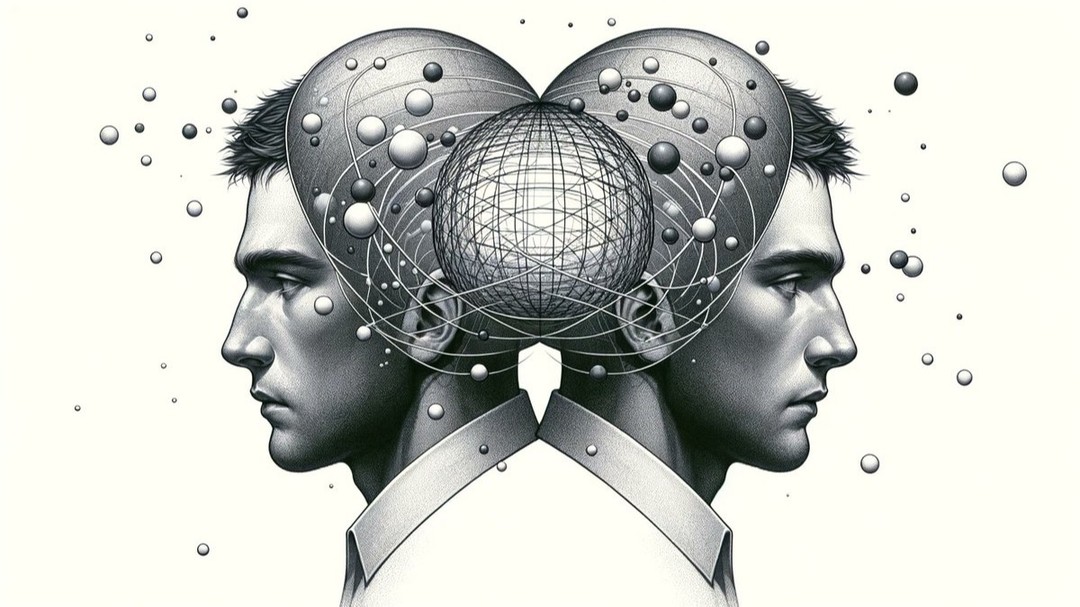1. はじめに
前稿ではカンタン・メイヤスーの思弁的実在論について、ハイデガーやドゥルーズの存在論の視点からごく簡単な批判を試みた。今回のこの小論では野矢茂樹が『心という難問』(2016)で著した眺望論と相貌論からなる新手の実在論について、批判的な考察を試みたい。
野矢によれば、眺望論とは、知覚し感覚する経験を空間と身体という観点から捉え、経験の公共性を明らかにしようとするものだという。他方、相貌論の狙いは、空間と身体の関係の中で浮かび上がる眺望の経験を「意味」という観点から捉え、それをさらに「物語」として論じることで、そこに他者性の核心をあぶりだすことにあるという。そして、これら眺望論と相貌論によって私たちの経験を素朴実在論的に捉えなおし、私と同様に他者も実在そのものの世界を共同的に経験しているという実感を掬いとろうとする。このような野矢の野心的な試みは、20世紀までの哲学が持った相関主義的な意識的態度に対するアンチとして立てられた新しい実在論の一つの類型と考えていいだろう。 見るものと見られるものに世界が分かれ、見るものは表象を通してしか世界に触れることができない。表象の背後には決して意識では触れられない物自体の実在世界がある————それが、カント以来の近代哲学が持った思考の大前提だった。しかし、野矢は世界とは見るものと見られるものとが未分離な一つの全体であることを、素朴実在論的な場所で示そうと試みているわけだ。こうした野矢の斬新な発想が果たして従来の哲学を乗り越えられるだけのポテンシャルを持つものなのかどうか、さしあたって、この小論では、空間と身体の関係に関わる眺望論にのみ議論を絞り、その論点をメルロポンティの空間論、さらにはドゥルーズの他者論といった、存在論の哲学者たちの論点から再度、検討し、野矢の実在論が等閑にしている問題点を幾つか指摘してみたいと思う。
2. 知覚的眺望と感覚的眺望
眺望論を論じるに当たって、野矢はまず眺望を“知覚的眺望”と“感覚的眺望”の二つに分け、世界のあり方をW、対象のあり方をo、対象との空間的位置関係をs、身体に関わる要因をb、意味に関わる要因をmとして、それらを関数関係に見立て、次のように書き表す。
W=f (o,s,b,m)
知覚的眺望は、この関数関係で言うなら、対象のあり方oとその空間的位置関係sだけで決まる関数W=f (o,s,)で規定される。つまりは、対象の見え姿をどんな空間的位置から見ているか、その視点によって眺望は規定されるということだ。こうした考え方によって、知覚的眺望論では、視点とは「世界の中にある単なる一地点にほかならない」(※1)ものとされ、それは人称を欠いたまったく公共的なものとなり、視点において〈誰が〉見ているのかといった要因は不要なものとされる。
しかし、このように、知覚的眺望を非人称的なものとして了解とすることは、知覚の現場そのものを存在論的差異と見なす存在論の立場からは到底、認められるものではない。知覚的眺望というからには、身体と対象が作るその位置関係の間に生き生きとした知覚が立ち上がっていなければならない。野矢は「知覚における眺望点とは、対象との位置関係(どこにいて、どちらを向き、なんと接触しているのか)であり、誰もがその眺望点に立ちうる」(※2)と何の説明もなしに断言するのだが、この眺望点なるものが自己と他者において果たして同質のものであるかどうかは甚だ疑わしい。なぜなら、自己と他者の関係においては、視点は決して並列的に存在するものではないからだ。 確かに、他者一般に限るなら、視点は時空上の一点一点にあたかもカメラのようにして張り付いているものと見て取れるが、自己にとって、自分自身の視点とは、カメラというよりはスクリーン(知覚正面)として現れるほかなく、自己は、決して、その視点の位置を外的に「点」として経験することはできない。言い換えるなら、自己にとっては、自分の視点などといったものは決して客観的に確かめることのできないものなのである。自己視点は、そこで世界が開く特異性の「絶対的零点」のごときものとして経験されているものであり、だからこそ、われわれはそこに〈わたし〉という一人称を与えているのであって、野矢のように、知覚的眺望を〈対象のあり方〉と〈対象との位置関係〉の関数のみで表現することは、こうした特異性としての自己を失わせ、視点を単なる対象の位置と変わらないものへと還元する愚行に等しい。つまり、野矢のいう眺望点においては、決して眺望は形成され得ない、ということだ。
その一方で、野矢は、眺望がひとたび個別の観測者の身体の前に実現化されたなら、先ほどの関数W=f(o,s)は身体に関わる要因をbを獲得し、知覚的眺望はW=f(o,s,b)という関数で規定される感覚的眺望へと変わり、そこに私秘的・現実的・人称的な知覚が現れると考える。
この議論もとってつけたようで、知覚の立ち上がりを先行する場と考える実存的立場からはまったく同意できるものではない。ここで”感覚的”眺望というからには、この身体に関わる要因bには、ベルクソン的にいうならイマージュの働きが含まれている必要がある。でなければ、感覚は時間的前後の脈絡さえ持たない、孤立した瞬間、瞬間のフラッシュバックのようなものにしかなり得ないだろう。しかし、野矢の立論では、この身体に関わる要因bに持続を含むイマージュの働きが考慮されている気配はまったくない。感覚的眺望を単なる外延空間と身体の出会いの場と見るのであれば、野矢はそこで眺望される風景を存在者的な対象としてしか見ておらず、存在論的な現象などは一切考慮していないことになる。存在論的な現象とは決して知覚可能なものではなく、ハイデガーに言わせれば「あらゆる知覚可能な現象に先だってあらかじめ、知覚可能な現象のために現れているもの」(※3)なのである。存在論的思考から指摘するならば、野矢が空間的位置を規定する関数W=f(o,s)に無条件に与えている空間の延長的性質も、本来は存在によって与えられたもの[es gibt]として考えなければならず、外延的な空間を無条件 に前提とするなら、それは存在的思考特有の悪しき形而上学としての超越を免れていないことになるだろう。(※1)
3. 眺望論には<奥行き>と<他者-構造>が存在していない
このような、野矢の眺望論における空間に対する思考の不徹底さは、メルロポンティやドゥルーズの空間論からも容易に指摘できる。メルロポンティが空間を思考する中で自らに課した課題は、経験的事物を超越した先験的、幾何学的空間と、経験論が主張するような通常の物理的な経験的空間との差異をどのように乗り越えるかということにあった。この両空間の関係は、野矢が語る知覚的眺望における無視点的眺望をなす空間と、感覚的展望における有視点的眺望をなす空間との関係に極めて近い。
空間と身体の関係について現象学的に深く思考したメルロポンティならば、感覚的眺望が文字通り感覚的なものとなるためには始元的な「奥行き」を絶対条件として挙げることだろう。メルロポンティにとっては、「奥行きこそ、空間の他のどの次元にもましていっそう直接に、[客観的]世界から来る偏見を投げ捨てて、世界のあらわれ出る始元的な経験を見直すようにわれわれを強いるもの」(※4)であり、ドゥルーズの空間論においても、この「奥行き」を巡る考え方はメルロボンティと一致しており、ドゥルーズは『差異と反復』の中で、この「奥行き」を「深さ」と言い換え、次のように綴っている。
「さて、深さはその本質からして、延長の知覚の中に巻き込まれているということは明らかである。すなわち、深さについても、様々な距離についても、物の外見的な大きさから判断が下されるわけではなく、反対に、まず深さが、それ自身において、もろもろの距離を包み込んでいて、それら距離が今度は、外見的な大きさとして繰り広げられ、延長として展開されるのである。」(※5)(※3)
野矢が語る眺望論の空間には、こうした始元的経験としての「奥行き」に対する言及がまったく存在していない。「奥行き」なきところに、いかにして感覚的眺望が成り立つというのか。深さとしての「奥行き」が空間に考慮されていない時点で、野矢が語る知覚的眺望は端から破綻してしまっているのではないだろうか。加えて、このように始元的な「奥行き」を欠いた眺望のなかでは、必然的に、他者の存在も無視したものとならざるを得ないだろう。このことは、野矢が「有視点把握が無視点把握に支えられている」(※6)と断言して、他者の視点を単に経験的他者のレベルに留め見ているところからも予想できる。 ドゥルーズによれば、他者とは「わたしの知覚野の中に現れる客体ではなく、わたしを知覚する別の主体でもなく、他者とは何よりもまず、それがなければわれわれの知覚野の総体が思うように機能しなくなる様な、知覚野の構造そのもの」(※7)である。このことは、存在論的に他者存在について考えるなら、他者とは、まず第一に、自己に知覚野の構造を与える超越論的な構造として機能していることを意味している。要は、他者とは自己にとっては経験的な存在である以前に、超越論的な存在であるということだ。こうした他者概念を持つドゥルーズにとって、眺望される対象は、野矢の言うような空間と身体の出会いのもとに与えられる所与などでは到底ない。むしろ、そのような出会いをさせるものそれ自体(超越論的なもの)が、対象を生成していく側に位置しているのである。ドゥルーズは「他者に関する哲学的理論の誤りは、他者を特異な客体に還元し、あるいは、もうひとつの主体へと還元してきた点にある」(※8)と常々警告を発していたが、空間的な眺望を語る以前に、わたしたちは世界の眺望を可能にする超越論的な構成としての、このような〈他者-構造〉について思考する必要があるのだ。
野矢はこうした超越論的な他者に何一つ触れることなく、『心という難問』の最後で次のように自身の論を締めている。
「知覚は世界を意識の内に取り込んだ表象ではない。私は、そして他者は、誰も意識の繭に閉じ込められてはいない。意識の繭など存在しない。私と世界を、そして私と他者を隔てる絶対の壁は存在しない」(※9)
野矢の眺望論に決定的に欠けているのは、そもそも眺望として立ち現れてくる世界がどこからやってきたのかというその起源に対する考察ではなかろうか。野矢の語る世界には肝心の生成の場所がどこにも見つからないのだ。存在論的思考に立脚するなら、本来、「奥行き」の中で持続する自己と他者それぞれの心が、幅と奥行きが等価な関係に置かれた素朴実在論的な延長的空間において、連続的に接続しつつ、公共的な世界へと開かれることなどまずありえない。自己と他者それぞれの心は奥行きとしての強度的空間を通じて内包(モナド)化し、そこで互いが互いを映し合いながら、その映し合いによって繰り広げられてくる外化のトポロジーを通して、世界は〈時-空〉化し、事物の眺望を一つの出来事として世界へと開いてくるのである。そこで展開しているトポロジーには経験的他者というよりも、わたしたちがまだ出会ったことのない全く別のあり方をした他者空間が活動していると想像できる。野矢は、あまりにも他者との出会いに対して性急すぎる。眺望論が提示する空間はあまりにも平坦すぎるのだ。このような空間のなかでは、世界で活動する物の秘密が見えてくることは決してないだろう。
〈参考文献〉
- (1) 野矢茂樹 (2015)『心という難問 空間・身体・意味』講談社,78
- (2) 野矢茂樹 (2015)『心という難問 空間・身体・意味』講談社,117
- (3) マルティン・ハイデガー(2005)『ツォリコーン・ゼミナル』みすず書房,8
- (4) モーリス・メルロポンティ(2007)『知覚の現象学』みすず書房,78
- (5) ジル・ドゥルーズ(2007)『差異と反復・下』 河出文庫,167
- (6) 野矢茂樹 (2015)『心という難問 空間・身体・意味』講談社,102
- (7) ジル・ドゥルーズ(1986)『原子と分身』哲学書房,26
- (8) ジル・ドゥルーズ(1986)『原子と分身』哲学書房,25
- (9) 野矢茂樹 (2015)『心という難問 空間・身体・意味』講談社,341